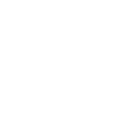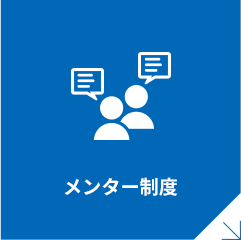採用情報
働き方について
“サラリーマン”として農業に携わる。
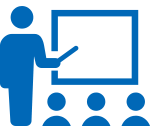
教育研修
入社時の新人社員研修、シーズンが始まる前の栽培研修や安全講習、ヒューマンスキル向上を目指す階層別研修など。そのほか、社員の成長に合わせて外部セミナーへの参加も促しています。そこで学んだことを改めて自分の中に落とし込み、後輩につなげて、全員の知識にできるよう取り組んでいます。
×
資格取得支援
入社時に必要なのはマニュアル車も運転できるMT免許です。その後は順次、作業をする上で必要となる資格にチャレンジ。例えば、農耕車の運転に欠かせない大型特殊免許の取得などを、個々の適性やスキルを考慮しながら勧めていきます。なお、資格取得にかかる費用はすべて会社が負担しています。
×
自己研鑽休職制度
申請すれば、12月から3月の農閑期に長期休暇の取得が可能。その間の給与支払いはありませんが、社会保険は加入のままです。この制度を利用し、冬はスキー場に勤務しながらウィンタースポーツを楽しむ社員も。また短期留学を試みたり、別の農場で異なる農業を体験したりと、活用の仕方は様々です。
×
キャリアパス
4段階の職位と、キャリアパスの「見える化」。会社が認めれば昇格も可能です。また、個人の目標、行動評価、職務評価の3カテゴリーによる人事評価制度を整え、必要な技能と自分の現況が分かるスキルマップを導入。面談ではそれらを用いて、目標達成への具体策をともに考えます。
×
副業OK
申請すれば副業もOK。農閑期となる冬にスキー場で働くケースが多いようです。なかには、時期を問わず1日の時間をやりくりし、当社の勤務を終えてからアルバイトに向かう人も。ただし農繁期の場合は、掛け持ちによる疲労で事故につながることのないよう、事前にしっかりとその旨を確認、指導します。
×
メンター制度
先輩社員がメンターとなり、新入社員が抱える業務への不安や悩みを聞き取りながら手厚くサポート。もちろん、仕事以外の部分も必要に応じてフォローします。問題が生じたらトップ陣に報告し、担当業務を調整するなどして解決へ。誰もが安心して働くことのできる職場づくりに努めています。
×
一年の流れ
穂海の一年は、農作業の流れとともに進行します。田植えや稲刈りといった一大業務の前後にも、スムーズな作業を支える様々な仕事が。季節を追いながら、その一連をご紹介しましょう。
春|3~5月

残雪残る3月上旬から、施設や機械の準備を始めます。
設備や機械の準備
雪解けとともに作業スタート!
3月中旬から、トラクターや田植え機といった圃場で使う機械と、苗づくりで使用する設備の準備をスタート。それらを組み立て、正常に稼働するかをチェックして、作業中のトラブル防止と安全確保に努めます。

4月から播種や湯温消毒など、苗の準備が始まります。
播種・温湯消毒・苗の準備
古くから「苗半作」と言われる最重要作業
水稲において苗づくりは肝。3月下旬から種まきを始め、温湯消毒、浸種などの多工程を踏み、芽出しの準備を行います。発芽したら苗代に並べ、天候を見ながら霜対策をするなどして大切に苗を育てます。

田植えは5月上旬から6月上旬までの約1か月間!!
田植え
いよいよ、約1カ月間の田植えに突入!
播種と並行して、圃場では耕運や代掻きなどの機械作業が行われます。圃場と苗の準備が整ったら、いよいよ田植え。早い品種から順に1カ月ほど作業は続きます。全社員が一丸となり、チームワークで乗り切りましょう。
夏|6~8月

夏の間は草刈りなどの中間管理!
草刈り・圃場の管理
夏のメイン作業は草刈り
田植え後の圃場はそれぞれの担当者が管理します。稲の生育状況を観察し、必要に応じて肥料を投入。メインの草刈りは、炎天下でのタフな作業が続きます。また、秋に向けて排水用の溝をつける「溝切り」もこの時期に。
秋|9~11月

ようやく収穫の季節!稲刈りは8月下旬から11月上旬まで続きます。
稲刈り
待ちに待った収穫は2カ月半の長丁場
半年間の仕事が実を結ぶときです。残暑厳しい8月下旬から初雪の迫る11月上旬まで、収穫は2カ月半に及ぶ長丁場。稲刈りチームが機械で刈った稲を、乾燥調整チームがライスセンターへ運び、そこで乾燥させます。

出荷後は外食や中食などの業務用米として消費者のみなさまへ。
出荷
大型トラックで全国のお客様へ
乾燥後、籾摺りと選別を経て出荷用袋に充填された米を全国へ届けます。年間の収穫量はおよそ720トン。データをまとめながら在庫を管理し、正確な入出庫を徹底しています。
冬|12~2月

一年の最後は総括会議で締めくくり!
総括会議
一年を振り返り、締めくくる日
オフシーズンに入ると、一日かけて総括会議を行います。まずは一年を振り返り、当初の計画と結果を検証。評価できる点や新たに見えた課題などを全社で共有し、翌年の作業計画に反映します。

冬の間は機械や農機具のメンテナンス
メンテナンス
長く使えるよう機械の手入れも念入りに
春から使用してきた機械をメンテナンス。作業ごとの専用機が多いため、手入れをする機械もかなりの数にのぼります。また雪深い地域だけに、冬はどんな作業をするにもまずは除雪から始まるのが常です。
未来の農業を作りましょう!